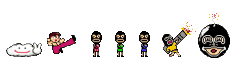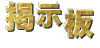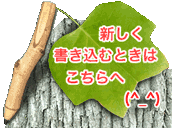突然ですが、古墳のお話です
きのう、埼玉県行田市にある、「さきたま古墳群」を見に行ってきました。5世紀から6世紀にかけての、前方後円墳や丸墳があわせて8個もあります。特に有名なのは稲荷山古墳で、ここから出土した「金錯銘鉄剣」は国宝となっています。これらの埋蔵品は古墳群の横にあるさきたま資料館に展示してあるので、いつでも見ることができます。この鉄剣を作った豪族、ヲワケの臣(おみ)は、当時の国造(国のみやつこ、今の県知事かな?)で、大和のワカタケル大王(雄略天皇)に仕えていたんだって。このころには、「氏姓制度」という支配体制が出来上がっていて、権力者、支配階級と、下層階級、さらに奴(やっこ)という奴隷のようなものまでいたらしい。(遠い昔、日本史で勉強したような記憶が・・・)
弥生時代に米作をするようになって、余剰作物を蓄えることが始まるとすぐさま、富の蓄積となって、持てるものと持たざるもの、富めるものと貧しいもの、強いものと弱いものに分かれていくんだね。
ま、なにはともあれ、いのししや、水鳥や、馬の埴輪がよかったよ!
弥生時代に米作をするようになって、余剰作物を蓄えることが始まるとすぐさま、富の蓄積となって、持てるものと持たざるもの、富めるものと貧しいもの、強いものと弱いものに分かれていくんだね。
ま、なにはともあれ、いのししや、水鳥や、馬の埴輪がよかったよ!